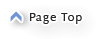アルザスのクリスマスツリーと本場のノエル
クリスマスツリー(Sapin de Noël)の最も古い記述は、アルザスにあり
 クリスマスツリーに関する最も古い記述は、1521年12月21日のもので、アルザスのセレスタにおいて、「クリスマスツリー用に使われる木(森)を見張っていた警備員に4シリングを支払った」というもの。
クリスマスツリーに関する最も古い記述は、1521年12月21日のもので、アルザスのセレスタにおいて、「クリスマスツリー用に使われる木(森)を見張っていた警備員に4シリングを支払った」というもの。
アルザスは、クレッシュ(キリスト生誕群像)に関する歴史も豊か。1420年、アルザスのアグノーの聖ゲオルギオス教会にクレッシュが置かれていたという古い記述が残っています。
冬の祝祭のシンボル、常緑樹のクリスマスツリー。
いつまでも青々としている木は、生命の象徴で、永遠を体現するもの。
樹木崇拝の文化は、昔からヨーロッパの異教徒の間で広く見られました。後に、キリスト教徒によって、針葉樹が天井からぶら下げられるようになり、さらに後に、鉢に入れて飾られるようになりました。
18世紀、アルザスにおいて、砂糖菓子や、クッキー、パン・デピスなどが飾られるようになり、クリスマスツリーの足元にクレッシュ(キリスト生誕群像)の小さい像が置かれるようになりました。
つまり、クリスマスツリー文化の発祥地はアルザスなのです。
19世紀、クリスマスツリーを飾る文化は、イギリス、フランスに広がり、20世紀ヨーロッパ中に広がりました。
ヨーロッパで最も大きい本物のモミの木が飾られるストラスブール
 11月~12月、毎年ストラスブールのクレベール広場には、ヨーロッパで一番大きな本物のモミの木が飾られます。
11月~12月、毎年ストラスブールのクレベール広場には、ヨーロッパで一番大きな本物のモミの木が飾られます。
2023年のモミの木は、高さ30m、重さ7トン、樹齢70年でした。
クリスマスツリーの飾りの意味:
三角形の木=三位一体
星=キリストの降誕を知らせたベツレヘムの星
丸い飾り=アダムとイヴが食べた知恵の樹の実
キャンディケイン(Jの形をしたキャンディ)=羊飼いの杖を表す。イエスキリストの頭文字
フランスで最も古いクリスマスマーケット/マルシェ・ド・ノエル(Marché de Noël)
 1570年から続くストラスブールのマルシェ・ド・ノエルは、フランスで最も大きな、最も歴史あるクリスマスマーケット。
1570年から続くストラスブールのマルシェ・ド・ノエルは、フランスで最も大きな、最も歴史あるクリスマスマーケット。
11月~12月、ストラスブールには、300軒の小屋が立ち並び、約1カ月間人々を魅了します。
キリストがこの世に生まれた日(ノエル)を祝う期間。
そして、アルザスのクリスマスマーケットに欠かせない人物は、サンタクロースでも聖ニコラウスでもなく、クリストキンデル(幼子キリスト)!
ストラスブールのマルシェ・ド・ノエルの名前は、「クリストキンデルスメリク(Christkindelsmärik)」と呼ばれ、「幼子キリストのマーケット」という意味です。
アルザスのクリスマスに欠かせないクリストキンデル(Christkindel)
 「クリストキンデル」とは、「幼子キリスト」という意味。
「クリストキンデル」とは、「幼子キリスト」という意味。
昔は、サンタクロースではなく、12月6日にカトリックの聖人、聖ニコラウスが贈り物を配っていました。
1570年、マルティン・ルターにより、年に1回子供たちに贈り物を配るのは、聖ニコラウスではなく、幼子キリストの役割とされました。
その幼子キリストを体現するのは、白いヴェールをかぶった女性で、モミの木の枝で作った冠と4本のロウソクを頭に載せています。(→これは、まさにアドベントクラウン)
ハンズ・トラップ(Hans Trapp)という、髭もじゃの男を従えています。
クリストキンデルは「光」を、ハンズ・トラップは「闇」を象徴しています。
クリストキンデルがプレゼントを配っている横で、ハンズ・トラップは、「悪い子はいねえかあ?」と低い声で脅し、今まで言うことを聞いてこなかった子供を泣かせます。(アルザスのなまはげ)
待降節/アドヴェントとは?
 「アドベント/待降節/降臨節(Avent)」とは、クリスマスまでの準備期間。クリスマスから数えて4週間前の日曜日からの期間。
「アドベント/待降節/降臨節(Avent)」とは、クリスマスまでの準備期間。クリスマスから数えて4週間前の日曜日からの期間。
この期間に、アドヴェントクラウン/アドヴェントクランツ(Couronne de l'Avent)のロウソクに毎週1本ずつ火を灯したり、子供たちが日めくりでチョコをもらえるアドベントカレンダーを贈ったりします。
モミの木やリース(輪)は、「永遠」を表し、キャンドルの火は、「世の光」として誕生したキリストを象徴しています。
宗派や家庭の事情にもよりますが、クリスマスツリーやクレッシュを用意するのも、この期間です。手作りクッキー(ブレダラ)もコツコツと作ります。
アルザスの文化に根付いていたクレッシュ(Crèche)
 クレッシュとは、キリスト生誕群像。マリア、ヨセフ、赤ちゃんのキリスト、牛、ロバなどからなり、キリストの降誕シーンを表現しています。
クレッシュとは、キリスト生誕群像。マリア、ヨセフ、赤ちゃんのキリスト、牛、ロバなどからなり、キリストの降誕シーンを表現しています。
一番最初の文に載せたとおり、アルザスにおけるクレッシュの歴史は深く、アルザスのスフレンハイム、ベッチュドルフの陶器工房では、今でも、このクレッシュを手作りで作っています。
昔は、お金がなかったから、クリスマスが近づいたら、毎年1個ずつ、像を買い揃えていきました。
アルザスのクリスマスに食べる料理
 食べる料理は家庭によって、様々です。
食べる料理は家庭によって、様々です。
アルザスでは、クリスマスイブの夜、クリスマスの日、聖ステファノの日(アルザスのみ祭日)に、特別な食事をとります。
以下が、代表的な料理です。
- 七面鳥/ホロホロ鳥の丸焼き
- フォアグラ
- スモークサーモン
- 魚介類(ロブスター、生カキなど)
- ブッシュ・ド・ノエル(丸太の形をしたチョコレートケーキ)
- ブレダラ(手作りクッキー)